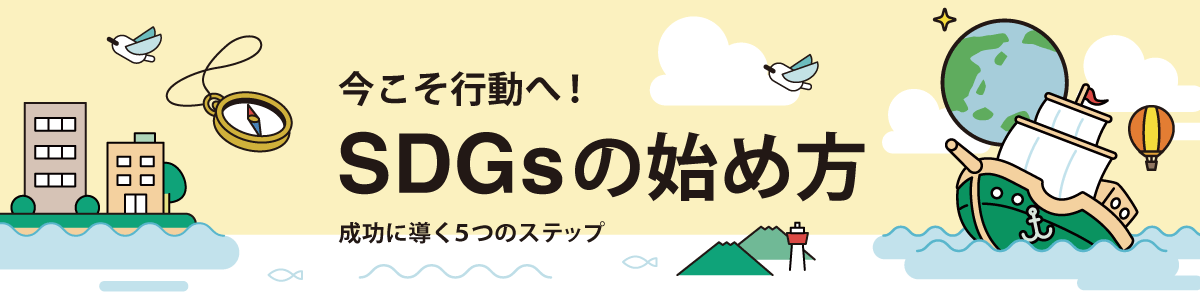従業員向けの金融教育、貴社ではどのような取り組みをされているでしょうか?
2022年には小学校、中学校、高校の授業にも追加されているほど重要視されている金融教育ですが、各企業にも従業員への金融教育が求められています。
では、どういった理由でそれほどにも金融教育が必要とされているのでしょうか。
なぜ金融教育が必要なのか、その理由
結論から言うと、従業員対象の金融教育を企業が実施することで、「SDGsにつながる社会的課題の解決」と「従業員の生活リスク対策」へ同時に対処することが可能となるからです。
従業員の金融リテラシーが低い場合、例えば住宅ローンを利用する際に他のローン商品との比較を行わず有利な借入機会を逃してしまうことや、高コストの消費者金融を利用してしまうなどの傾向が報告されています。これはつまり、大切な従業員が人生のあらゆる場面で必要となるお金の管理が出来ず、より豊かな暮らしを送ることが難しくなるということです。そこで金融教育を実施することで、企業としてこの課題の解決へ向き合うことができ、SDGsの「4.質の高い教育をみんなに」と「1.貧困をなくそう」等への取り組みになります。また従業員が安心して働ける職場を作ることにもなります。
実際に金融庁の報告書(※1)によると、味の素グループではウェルビーイング向上のための取り組みとして従業員を対象に金融教育を提供しています。これにより持株会の加入率が上昇するなど、従業員の金融リテラシーが高まっていると読み取れる結果が得られました。
もっと現実的な面としては、企業の導入している制度への直接的な影響も見逃せません。
企業の退職金制度は、企業が運用を行う確定給付年金の従来型から、今では従業員本人が運用を行う企業型確定拠出年金(企業型DC)などへ徐々にシフトしているのはご存じのとおり。その他にも、新NISA制度の開始やiDeCoなど、個人の、ひいては従業員自身が資産運用に触れる場面は確実に増加しています。にもかかわらず、金融リテラシーを身につけられていないことで、従業員がやみくもな運用をしてしまう、そもそも運用などの資産形成を避けてしまうことになるかもしれません。企業として、従業員のことを思い資産形成の機会を提供したとしても、それだけでは必ずしも十分とは言えず、金融教育や相談の受け付けといったケアを検討する必要があるでしょう。
なお、企業型DCについては、事業主に、加入者に対する投資教育の継続的な実施が努力義務として法定もされています。実施を怠った場合は罰則こそありませんが、それは事業主の義務が軽度であることを意味するのではなく、投資教育の内容の当否について一律の判断が難しいことから、罰則の規定を避けたに過ぎないことを意識しておくべきでしょう。
また、学校教育における金融教育が浸透する中で、従業員への金融教育の取り組みは就職先選定時に当たり前の要素となっていくことも考えられ、将来の人員確保にも影響を及ぼすと予想されます。
こういった将来のリスクに対処するためにも、金融教育をして金融リテラシーを高めることが必要とされているのです。
金融教育の方法
従業員に対する金融教育は必要ですが、それを行うリソースは必ずしも社内に備わっている必要はありません。金融教育の具体的な方法については、職域セミナーなどが挙げられます。実施については取引のある金融機関や、J-FLEC(金融経済教育推進機構)など、専門家の在籍する機関へ相談するのが確実です。
職域セミナーとは?
職域セミナーは、企業や団体が従業員向けに実施する金融教育の一環です。主に職場で行われ、専門家や金融機関の講師が登壇して、ライフプランニング、資産運用、年金制度、保険などのテーマを扱います。従業員が金融知識を身につけ、自身の将来設計や資産形成に役立てることを目的としています。セミナー形式は講義型が一般的ですが、ワークショップや個別相談を組み合わせることもあります。とくに日本では、老後の生活資金やNISA・iDeCoといった税制優遇制度への関心が高まる中、職域セミナーが金融リテラシー向上の場として注目されています。企業にとっても、従業員の生活安定が生産性向上につながる点で、重要な取り組みとなっています。
J-FLEC(金融経済教育推進機構)とは?
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、2024年4月に設立された認可法人です。金融教育を普及・推進するために設立された組織で、個人や企業、学校向けに幅広いサポートを提供しています。金融リテラシー向上を目的とし、セミナーの開催や教材の開発などを通じて、金融に関する知識やスキルの普及を目指しています。
企業がJ-FLECを活用するには、まず公式ウェブサイトの問い合わせ窓口を通じて相談しましょう。また、同機構はXやYoutubeにて情報発信もしています。こちらも検討材料にしてみると良いかもしれません。
従業員への金融教育が必要な理由と、その方法についてお届けいたしました。
ただし、教育を実施しても金融リテラシーが身に付かなければ意味がありません。そのため定期的に実施できる体制づくりこそが重要であり、SDGsへの取り組みにも繋がっていきます。
もちろん、りそなグループでも職域セミナーの相談を承っていますので、ご検討の際はお声がけください。
(※1) 金融庁「金融経済教育等の推進に向けた調査等支援業務(職域等における金融経済教育を推進するための手法等に関する調査)事業報告書」
SDGsについて、わかりやすく資料にまとめましたのでこちらもぜひご活用ください。