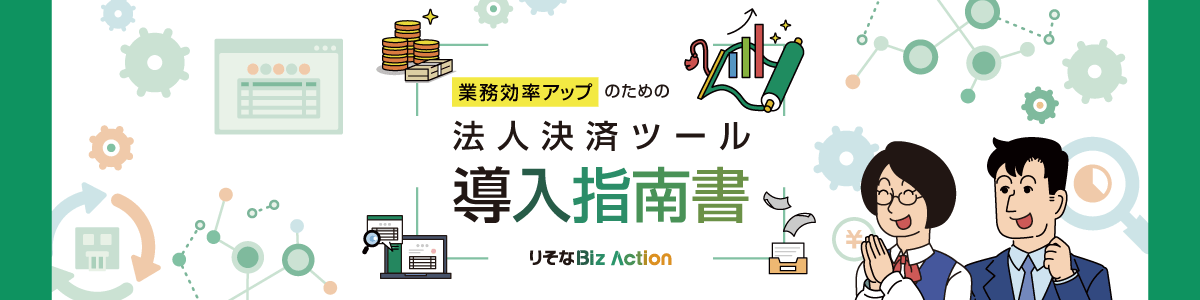自ら起業した中小企業の社長にとって、「従業員数100人」は一つの節目と言えます。事業の成長を実感し、活気の出てきた社内に充実感を覚えるでしょう。その半面、法的にやるべきことは増え、全体を掌握することは簡単ではなくなります。起業当初のやり方では通用しない課題や業務も多くあるはずです。従業員数が100人を超えたら、業務を効率化し、生産性を向上させることも考えていきたいものです。特に、経費精算は従業員が増えると担当者の負担も増加します。「経費精算にかかるリソースを他に振り向けたい!」と考える経営者は多いのではないでしょうか? 今回は、従業員数が100人を超えたら検討したい、経費精算を効率化する方法をご紹介します。
「100人」を超えると、やりがいも責任も大きく
事業の拡大に伴って人手が必要になり、戦力の充実がさらなる成長につながる・・・。
従業員が増えることは、会社の「生みの親」である社長にとって特別な達成感があるはずです。ただ裏を返せば、それだけ多くの人生を支える責任を負うということでもあります。従業員の家族まで考えると、さらに重みも増すというもの。
常用労働者が101名以上になると、次世代育成支援対策推進法により、仕事と子育てが両立できる環境を整えるなどの「一般事業主行動計画」の策定が義務付けられます。同様に女性活躍推進法では、女性の活躍に関する情報の公表が必須になっています。障害者雇用促進法に基づき、障害のある人の雇用も求められ、法定雇用率を下回った場合は納付金を納める必要もあります。
管理業務をアップデートする好機に
また、ガバナンスや人事労務の負担も大きくなります。部署を越えたコミュニケーションが難しくなる中、報告がきちんと上がる仕組みを築き、事情を抱えた従業員の要望に応え、多様な働き方やワーク・ライフ・バランスを充実させ、労務トラブルにも対応し・・・と、なすべきことは山積み。職場の環境整備に多くのリソースが割かれます。だからこそ、非効率な旧来のやり方を変えるべき好機です。
利益ゼロの業務にかかる、膨大なコストを圧縮するには
人件費換算で…1人「144万円」
中でも経費精算業務は、働く側にも、管理する側にも大きな負担。経費管理クラウドを提供するコンカーが2016年に発表した「サラリーマンの経費精算に関する実態調査」(※1)によると、76%のサラリーマンが経費精算を「面倒」と答え、理由には「領収書の保管」「入力作業」「領収書の糊付け作業」を挙げています。生涯で経費精算に平均52日を費やし、人件費では1人144万円に相当するといいます。利益を生まない作業に、多くの時間とコストがかかっています。
2016年の電子帳簿保存法の改正で、スマートフォンなどで撮った領収書のデジタル画像が原本として使えるようになりました。ただ、ペーパーレス化が進んでいる企業ばかりではなく、まだ多くの会社員らが、大量の紙を前に悪戦苦闘しているとみられます。
経費精算業務にありがちな「お悩み」は
経理担当者を悩ませるものは、どういうものでしょうか? まず、申請のプロセスが複雑なため、「申請」「承認」「差し戻し」と何度もやり取りを重ねがちなことがあります。通勤定期の区間など細かなチェックに追われるほか、働き方改革で出社の機会が減ると、申請用紙の処理が滞ることもあるでしょう。ルールの不徹底も心配の種です。また、先ほどの調査によれば、24%のサラリーマンが「経費の不正使用の経験あり」と答えています。
これらのこまりごとを一手に解消するのが、経費精算システムです。
経費精算システムの導入メリットとは
経費精算システムは数多くありますが、共通する代表的なメリットをみてみましょう。
まず、社内規定に反する申請を自動ではじき、差し戻しの手間を省くことができます。交通費なら、定期区間の運賃を自動で控除可能です。例えば、品川駅から東京駅まで定期で通勤している人が、東京駅から横浜駅に出張した場合、東京~品川間を自動で差し引くというもの。これにより、過剰に申請してしまうミスを防ぐことができます。
システムでは交通費の他、出張旅費や交際費、業務上必要な物品を購入した際の経費、福利厚生施設の利用料など、あらゆる処理を一元管理できるのが特徴。スマホなどにも対応しているため、外回りや出張中の空き時間で申請でき、時短とストレス軽減につながります。コーポレートカードとの連携で立替払いを減らし、不正利用も防げます。
従業員数100名の企業では、システム導入により経費精算業務のコストが約3分の1に減ったという事例も。ルーティンの多い管理業務を省力化することで、利益や価値を生み出す業務にリソースを配分でき、会社全体の生産性が高まるでしょう。
※1 コンカー「サラリーマンの経費精算に関する実態調査」(2016年6月10日発表)
法人決済ツールについて、わかりやすく資料にまとめましたのでこちらもぜひご活用ください。